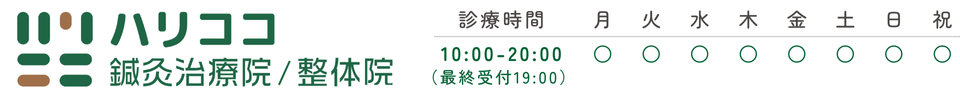冷たいものと腰痛の意外な関係①
〜アイスや冷たい飲み物が、腰痛を引き起こす?〜
夏になると、ついつい手が伸びてしまう冷たいアイスやジュース、氷のたっぷり入ったドリンク。暑さをしのぐためにも、キンキンに冷えた飲食物は魅力的ですよね。
でも実は、この「冷たいものの摂りすぎ」が、腰痛の原因になることがあるというのをご存じでしょうか?
「え?飲み物と腰の痛みって関係あるの?」と驚かれるかもしれません。
今回は、そんな“食生活と腰痛の関係”について、体の内側から見直す視点でお届けするシリーズ第1話です。
冷たいものが体に与える影響とは?
私たちの体は、本来「体温36〜37℃前後」の温かい環境の中で内臓や筋肉が正常に働くように設計されています。
ところが、冷たい飲み物や食べ物が体内に入ると、内臓は一時的に冷やされます。
これにより、
- 胃腸の働きが鈍くなる
- 血流が悪くなる
- 自律神経が乱れる
といった影響が出てきます。特に冷たいものを毎日のように大量に摂っている方は、知らず知らずのうちに体の中から冷えている状態に陥っているのです。
そして、この「内臓からの冷え」が、筋肉のこわばりや神経の緊張、さらには腰痛の誘発につながってしまうのです。
冷えと腰痛の関係性
なぜ、冷えが腰痛につながるのか?
そのメカニズムにはいくつかの視点があります。
1. 血流の低下
冷えによって体の末端や深部の血流が悪くなると、筋肉に十分な酸素や栄養が届かなくなります。すると、筋肉が硬くなりやすくなり、トリガーポイント(筋肉のしこり)ができやすくなるのです。
これが腰周りで起こると、慢性的な腰の張りや痛み、違和感として現れることがあります。
2. 自律神経の乱れ
冷たいものを大量に摂取すると、自律神経が乱れやすくなります。自律神経は、内臓の働きや筋肉の緊張のコントロールにも関与しているため、乱れることで腰回りの筋肉が過緊張状態になることもあります。
夜になると腰が重くなる、朝起きたときに腰が硬い…そんな方は、自律神経の影響も疑ってみる必要があるかもしれません。
3. 内臓疲労による関連痛
東洋医学的な視点では、内臓の疲れや冷えが筋肉や関節に“関連痛”として現れるという考えがあります。たとえば、冷えやすい腎臓の不調が、腰の重だるさや痛みに影響すると考えられているのです。
実際、鍼灸や整体の現場では「内臓の冷えと腰の痛みはリンクしている」と感じるケースが多々あります。
冷たいもの、どれくらいが“摂りすぎ”?
ここまで読んで、「そんなに冷たいものを摂ってないけど…」と思った方もいるかもしれません。
ですが、無意識に毎日少しずつ体を冷やしている人は意外と多いのです。
例えば、
- 朝起きてすぐ冷蔵庫の水を一気飲み
- 昼に冷たいそばやうどん
- 食後にアイスや冷たいお茶
- 夜寝る前に炭酸飲料やビール
これが毎日の習慣になっていると、知らず知らずのうちに内臓が冷えっぱなしの状態になっているかもしれません。
また、夏場に限らず冬でも、冷蔵庫で冷やした飲み物を年中口にしている方は要注意です。
腰痛持ちの方が見直すべき「食生活」
もしあなたが腰痛に悩まされていて、整骨院や整体に通ってもいまいちスッキリしない…と感じているなら、食生活や飲み物の習慣を見直してみることが回復のヒントになるかもしれません。
特に以下のような傾向がある方は、冷えによる影響を受けやすいと言われています。
- 冷え性
- 便秘や下痢を繰り返す
- 胃もたれしやすい
- 夏でも足が冷たい
- 腰が重だるい/じんわり痛む
これらに心当たりがあれば、次回のシリーズでは「具体的に何を避け、何を摂れば良いのか」という実践的な内容をお届けしていきます。
まとめ
腰痛は「姿勢」や「筋肉の使い方」だけでなく、「内臓の冷え」や「食習慣」とも深く関係しています。
身体の表面だけでなく、内側からも整えていくことで、より根本的な改善につながります。
腰の痛みがなかなか取れない…
マッサージやストレッチでは限界を感じている…
そんな方は、まずは「冷たいもの」を見直すことから始めてみてはいかがでしょうか?
次回【第2話】では、「冷たいものを減らすためのコツ」や「内臓を温める食事法」について詳しくご紹介します。
どうぞお楽しみに!
※本記事は、淡路島・ハリココ鍼灸治療院の臨床経験をもとにした健康情報シリーズです。気になる症状がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。